和漢三才図会/第7巻/人倫/鋳物師
| 解説 | 正徳5年(1715年) 鋳物は聖武天皇が東大寺の大仏建立にあたって銅製の大仏を鋳造したことを始まりとします。 鋳物は金属を溶解して、あらかじめ造られた型に流し込んで、器物を造る技法をいいます。 その技術者もしくは集団を鋳物師(いもじ)といいました。 この書では、鍋や釜の鋳物師の始まりは河内国我孫子、次に「江州ノ辻村」としてあり、鋳物師の中でも著名であったことがわかります。 |
|---|---|
| 資料種別 | 和書 |
| 地域 | 栗東・野洲地域 > 栗東市 |
| タイトル | 和漢三才図会/第7巻/人倫/鋳物師 ワカン/サンサイ/ズエ/7/イモジ |
| 著者 | 寺田良安/著 テラダ/リョウアン |
| 出版年(西暦) | 1715 |
| 出版年(年代) | 1715年[正徳5] |
| 出版社 | 岡田三郎右衛門/他 |
| 形態 | 27㎝×19㎝ |
| 件名 | 鋳物/伝統技術 イモノ/デントウ/ギジュツ |
| コンテンツID | 0501286 |
| IIIF マニフェスト | https://da.shiga-pref-library.jp/0501286/manifest |


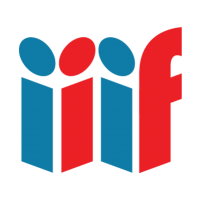 ビューアーで見る
ビューアーで見る